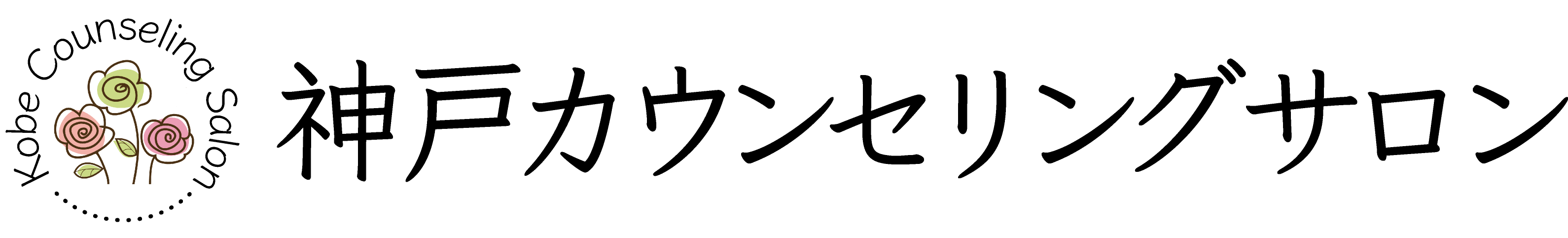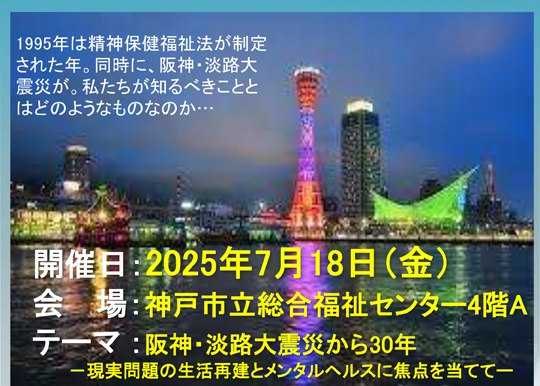
7月18日@神戸市立総合福祉センターで、参加して来ました。
その中の、
元 神戸新聞専門編集委員 現 神戸大学戦略企画室 特命准教授の磯辺康子先生の、
「人間復興の30年ー生活再建の現実と心のケアー」、
皆さんにもぜひ聞いて欲しい内容でした。
1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、
例えば、兵庫県こころのケアセンターが開設されたことなどは、
広く知られていること。
他にも、阪神・淡路を契機に、政府の危機管理が24時間体制になったりだとか、
被災者生活再建支援法(1998年)が制定されたりだとか。
多くの人の苦しみと、多くの人の尽力の上に、
こうして、今の私たちの生活があるのだと、あらためて感じました。
そして、阪神・淡路は、ボランティア元年とも言われていて、
実際、阪神・淡路には、
1年間でのべ137万人ものボランティアの方々が来て下さったそうです。
で、ボランティアには、スキルを持つ人だけが必要なのではない。
障害を持つからこそ、同じ立場の人の気持ちがわかることも。
「そこに居ること」「伴走すること」「居るだけボランティア」の存在も、
大切なのだと。
さらに、「被災者=支援される人」ではなくて、
被災した人達の、「何か役に立ちたい」「一緒に働きたい」思いについても、
伝えて下さいました。
それを受けて、この会を主催された、
日本福祉大学福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科の青木聖久教授からは、
「ヘルパーセラピー原則」という、何やら耳慣れない言葉が。
「セルフヘルプ」や「ピアサポート」にも通じる概念で、
「人を助けることで、自分が助けられている」という考えだそう。
「この人と一緒に居ると楽しい」「この人と一緒なら戦える」etc…
そんな風に思って貰えている自分がまんざらでもないのだ、
というお話には、自分の姿も重なりました。
以前読んだ、東畑開人さんの『野の医者は笑う 心の治療は何か?』(誠信書房/文春文庫)にも、
相談をしに来ていた人が、今度は相談を受ける側になって行くことで、
癒され、回復していくというようなくだりがあったのを思い出しました

最後、見事なボイスパーカッションを披露してくれたのは、
自身も阪神・淡路で家が全壊した、
異色の防災音楽ユニット “ブルームワークス”のKAZZさん♪
(私が心理学を教える、専門学校の生徒さんでもあります!)